地球の海はどこから来たのか?
地球の海は、濃度3%前後の塩などが溶け込んだ水(海水)でできている。海は地表の70.8%を占め、これらは全てつながっている。
地球だけではない、火星には、地質時代には海があった可能性がある。 また、木星や土星の氷衛星のいくつかは、氷の地殻の下に液体の水の海があると推測されている。エウロパ、ガニメデ、カリスト、タイタン(水とアンモニア)、エンケラドゥスに海がある可能性が高い。海は地球だけのものではなかった。では、地球の海はどこから来たのだろう?
地球はその形成時に、ジャイアントインパクトがあり、地球軌道の外側から大量のH2Oを含む天体が衝突したことで、海ができたと考えられる。だが、そう考えた場合、地球の総質量に対する海の割合は0.02%ほどで、かなり少ない値であり、残された水素はどこに行ったのか?…という謎があった。
今回、東工大の地球生命研究所(ELSI)の廣瀬敬 教授らの研究チームは、マントルの融点を決定し、そこからコアの化学組成を導きだす研究を行った。その結果、マントルの溶融温度は従来の研究から見積もられていたよりも600Kほど低い約3600Kと判明。
従来提唱されてきたさまざまな学説の中で(主なものとして硫黄、酸素、水素)それだけの融点降下を実現できるのは水素だけであることが導き出された。
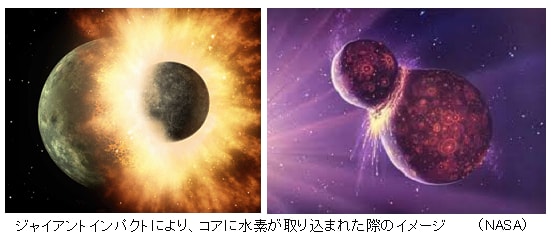
地球のコアには海水の80倍の水素が含まれている
東京工業大学(東工大)は1月17日、地球のコアに海水の約80倍の量の水素が含まれていることを研究により明らかにしたと発表した。
同成果は、同大大学院理工学研究科博士課程3年の野村龍一氏と同 地球生命研究所(ELSI)所長の廣瀬敬 教授、同大大学院理工学研究科の上野雄一郎 准教授、京都大学大学院理学研究科の土`山明 教授、同 三宅亮 准教授、高輝度光科学研究センター(JASRI)の上杉健太朗氏、同 大石泰生氏、海洋研究開発機構(JAMSTEC)らによるもの。詳細は、米科学誌「Science」に掲載される予定で、それに先んじて1月16日付(米国時間)で「ScienceXpress」に掲載された。
ELSIは地球の成り立ちから生命の起源を探ることを目的に2012年に設立された研究所。生命の起源については、一般的には生物学者などの視点から検討が行われてきたが、同研究所では、地球がどうやってできたのか、といった視点からその謎に迫ろうというアプローチをとっている。
地球の質量は岩石で構成されるマントルが約7割、順合金で構成される液体コア(外核)が約3割を占めると言われているが、コアの化学組成はこれまでよく分かっておらず、1952年に地球科学者であるフランシス・バーチ博士が外核の密度が鉄ニッケル合金である場合の密度と、観測で得られる密度の差が1割程小さくなることを指摘して以来、約60年にわたって、純鉄以外に何が含まれているのか、ということを巡って論争が繰り広げられてきた。
地球のコアの化学組成は長年の謎
また、宇宙には揮発性物質が凍って固体になるか、蒸発して気体になるかの境目「スノーライン」があるが、地球はその内側(H2Oは気体になる)にあるにも関わらず、水が蒸発せずに海が存在している、という謎もある。地球の形成時に生じたジャイアントインパクトにより、スノーラインの外側から来た大量のH2Oを含む天体が衝突したことで、海ができたと考えられるが、そう考えた場合、地球の総質量に対する海の割合は0.02%ほどで、かなり少ない値であり、残された水素はどこに行ったのか、という謎があった。
廣瀬教授は、「この0.02%という比率が地球という星の奇跡を生んだ。海の質量が少ないことにより、海の深さが限られ、陸と海の共存が起き、多様な環境を発生させ、陸地にあるリンやカリウムが海に流れ出し(海水中のリンやカリウムはわずかしかない)、それが生命の誕生や進化に影響を及ぼした可能性があると考えている」とし、もし、海水の量が2倍になったと仮定した場合、地球上から陸地は現在の4000m級の山々より上しか残らないこととなり、陸上生物が果たして存在しえたかどうか怪しいことになるとする。
今回の研究は、こうした謎の解明に向けたもので、マントルの融点を決定し、そこからコアの化学組成を導きだすことを目的に行われた。具体的には、レーザー加熱式ダイアモンドアンビルセルを用いて地球深部と同等の圧力と高温を、マントル最下部層の主要後部であるポストペロフスカイトに発生させ、その融解温度をSPring-8の高輝度X線を利用した高解像度マイクロトモグラフィ(CT)撮像技術を用いることで特定した。
今回は高温・高圧技術にはやぶさの試料分析でも用いられたX線CT撮像を組み合わせることで、試料内部のわずかな溶け始めている部位を発見。その痕跡を調べることで、マントルの融点を決定した。
その結果、マントルの溶融温度は従来の研究から見積もられていたよりも600Kほど低い約3600Kと判明。この結果から、マントル最下部層と隣接するコアの最上層部の温度も従来の推定値よりも400K低い3600K以下であることが必要となり(純鉄の場合、融解温度はコア最上部で約4200K)、従来提唱されてきたさまざまな学説の中で(主なものとして硫黄、酸素、水素)それだけの融点降下を実現できるのは水素だけであることが導き出されたのだ。
今回の実験から導き出されたマントルの融点(マントル最下部層の気圧は135万気圧)。従来見積もられていた融点に比べかなり低いことがわかる。
鉄とシリコンに取り込まれた水素
一方、宇宙存在度(太陽系の始原物質の元素組成)に基づく地球全体の元素組成を見た場合、シリコンの量はマントルの内部だけでは不足しており、結果としてコアに6重量%程度含まれていると考えられていることから(ミッシングシリコン)、鉄とシリコンを基本に、そこに新たに判明した水素を含ませ、その量を計算した結果、コアには重量にして0.6%、原子数換算では25%の水素が含まれていることが判明したという。
マントルの融点よりもコア最上部が低くないとマントルが溶けてしまうので、それを元に組成を導き出すと、議論の主流となってきた硫黄、酸素、酸素の内、水素だけが融点よりも低く、かつ観測で得られた密度を満たすことができることが判明した。
この0.6重量%の水素がコアに入るためには、地球形成期のマグマオーシャン中に、地球全体の1.6重量%ほどの水が必要であり、これは0.02重量%の海水に比べ約80倍に相当することを意味する。ちなみにこの0.6重量%という値は、
H2O+2Fe→2FeH+FeO
の化学反応がマグマオーシャン内部で生じた際の平衡状態となる値であるという。
この結果について廣瀬教授は「惑星形成時に地球は大量の水を有していたが、その大部分がコアに水素として取り込まれた可能性が高い。これにより地球表層から、ほとんど水がなくなり、地球のダイナミクスが表層に影響を与え、結果として陸地と大気を生み出した」としており、生命の元となったリンやカリウムを地中から水中に運び、そこから生命を生み出す基盤が作りだされた可能性があるという。
なお、今後の研究については、この平衡状態の詳細の決定や、ほんとうにこの化学組成で地震波速度から得られているデータと一致したものが得られるのかといった研究のほか、ほんとうに生物が生み出されるのか、といった点を進めていきたいとしている。
大量の水素がコアに取り込まれたことにより、地球表層に残されたわずかな水が海と陸地を作り、そして生み出された大気との組み合わせにより生命の起源となる仕組みが作りだされた可能性が示されたという。
ジャイアント・インパクト
ジャイアント・インパクト説(giant impact theory)とは、地球の衛星である月がどのように形成されたかを説明する、現在最も有力な説である。衝突起源説とも呼ばれる。
この説では月は原始地球と火星ほどの大きさの天体が激突した結果形成されたとされ、この衝突はジャイアント・インパクト(Giant Impact、大衝突)と呼ばれる。また、英語ではBig Splash や Big Whack と呼ばれることもある。原始地球に激突したとされる仮想の天体はテイア(Theia)と呼ばれることもある。
ジャイアント・インパクト説以前は1898年にジョージ・ハワード・ダーウィンが提唱した遠心力による溶けた原始地球からの月の分離を説いた「分裂説」が受け入れられていたが、この説では分離初期の状態を説明出来なかった。
1946年にハーバード大学の教授で地質学者であるカナダ人のen:Reginald Aldworth Dalyが月の誕生は遠心力による分離ではなく天体衝突によるものであるとの説を唱えたが、発表当時は受けいれられなかった。その後1975年に衝突説がウィリアム・ハートマン (William K. Hartmann) とドナルド・デービス (Donald R. Davis) によって科学雑誌『Icarus』に発表した論文で再提唱され、今では広く受け入れられている。
火星ほどの惑星が衝突か?
ジャイアント・インパクト説によると、地球が46億年前に形成されてから間もなく火星とほぼ同じ大きさ(直径が地球の約半分)の原始惑星が斜めに衝突したと考えられている。
原始惑星は破壊され、その天体の破片の大部分は無色鉱物に富んだ地球のマントルの大量の破片とともに宇宙空間へ飛び散った。破片の一部は再び地球へと落下したが、正面衝突ではなく斜めに衝突したためにかなりの量の破片が地球の周囲を回る軌道上に残った。軌道上の破片は一時的に土星の環のような円盤を形成したが、やがて破片同士が合体していき月が形成されたと考えられている。
現在のコンピュータシミュレーションによる推定では、このような場合では1年から100年ほどで球形の月が完成するとされている。また最近のシミュレーションでは、月が一つにまとまるまでの時間は早ければ1ヶ月ほどだとする結果が出ている。誕生したばかりの月は地球から僅か2万kmほどのところにあり、それが徐々に地球との間の潮汐力の影響で地球から角速度を得て遠ざかり、現在のように地球から平均38万km離れた軌道まで移動したと考えられている。
またこの影響で、月が誕生した当初は1日5時間から8時間ほどだった地球の自転速度が現在のような1日24時間の速度になったとされる。現在でも地球と月は1年に3.8cmずつ遠ざかり、地球の自転速度も少しずつ遅くなっていることが実測されている。(Wikipedia)
参考 Wikipedia: ジャイアントインパクト マイナビニュース: 地球のコアには海水の80倍の水素が含まれている![]()
![]() ←One Click please
←One Click please
��潟�<�潟��